小説 | 疵

-
著 / 出口臥龍
出口様は他にも書籍を作られています。
内容紹介(一部)
序章
「サァーラー、沙羅ちゃ?ん」
遠くで母の明子が呼んでいる。
マックスを抱いた上城沙羅は、母の呼び声を振り切るように江戸川の土手を急いだ。小柄で痩せっぽち。おでこが秀でて、くりくりした目が利発そうだ。
マックスは隣りの中井家の飼い犬で、白いポメラニアンのオスだ。一昨日からの集中豪雨のために、普段は野球場として使われている河川敷も、逆巻く濁流の下に沈んでしまった。
武蔵野線の鉄橋が架かっている。首都圏を囲むように、郊外を走っているJR線だ。江戸川の東が千葉県のN市、西が埼玉県のM市。鉄橋の手前に、クルマ用の橋と歩行者専用の狭い橋が二つ並んで架かっている。
沙羅は歩行者専用橋に足を踏み入れた。荒れ狂う川の流れに足が竦んだ。ごぉーっという唸りが、低く垂れ込めた暗い雲との間でこだまし、恐怖心を煽る。
赤いカーディガンの胸に隠すように、沙羅はマックスを抱いた。異常を察してか、マックスの前足が沙羅の胸にしがみつく。ブラウスを通して、爪が胸の疵に食い込むようだった。
一台の軽自動車がN市のほうから走ってきた。
「あれ、沙羅ちゃんじゃないの?」
運転していたのは南絵梨の母・智子だった。絵梨は沙羅とは三年一組の同じクラスだ。成績は優秀だが、沙羅にはかなわない。無口で暗い陰を感じさせた。
「ホントだ。声掛けてみようか」
助手席の絵梨が、母の顔を見上げた。
「でもあんた、沙羅ちゃんは嫌いなんじゃない」
智子の、赤ぶち眼鏡の奥が、キラリと光った。
クルマを追い越すように、武蔵野線の電車が近づいて減速した。鉄橋を渡りきったところがJRの駅だ。
電車が過ぎ去ってから、沙羅はマックスの腹が下になるように抱きなおした。
「ほら、凄いでしょ」
マックスの視界で泥水がのたうつ。首を捩じって、沙羅の顔を見上げた。救いを求めるかのような瞳だ。
「かわい?い。私だけのマックス」
(以下略)
第一章
三年前の冬だった。
ある国立大学の理化学研究所に勤務していた上城操は、妻の明子、それに一粒種の沙羅とともに、大学の職員寮でつつましく暮らしていた。
世田谷の砧公園の傍にあった鉄筋コンクリートの二階建てだ。公園はごみ焼却所建設の見返りに造られた広大なもので、休日になると三人は半日近く芝生の上で過ごした。
操は名前とは裏腹に、長身で精悍な男だった。学究らしく、物事に凝ると、とことん突き詰める性質でもあった。研究所では海外の文献を読み込む仕事が中心だった。夕方ともなると、肩に大きな石を背負ったように疲労が蓄積する。
学生時代にはワンダーフォーゲル部に所属していて、富士山の裾野をよく歩き回った。妻の明子はワンゲル部の後輩だ。明子の少し翳のある美しさに惹かれていた。いつしか明子を富士の姿に重ねるようになった。
研究の区切り毎に、無性に野山に浸りたくなる。特に富士には愛着があって、あの雄大な稜線を眺めているだけで心が癒された。
近くに東名高速の用賀入り口があった。ふと思いついて明子に声を掛けた。
「なぁ明子、クルマ買ってみようか。中古車でもローン利くんだろ」
「ローンだったらなんとかね。でもマイホームは遠のくわよ」
「やたら富士を見たくなる時があるんだ。用賀からなら焼津でも一時間くらいで行けるんじゃないかな」
沙羅を肩車して、操は近くの中古車センターを覘いた。沙羅は操の髪を手綱のように握り締め、はしゃいだ。
(以下略)
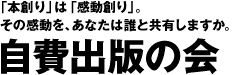










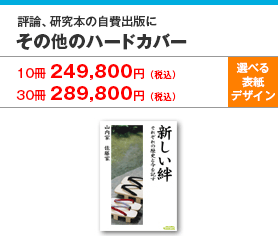
 円周率いろいろ
円周率いろいろ 伝兵衛
伝兵衛